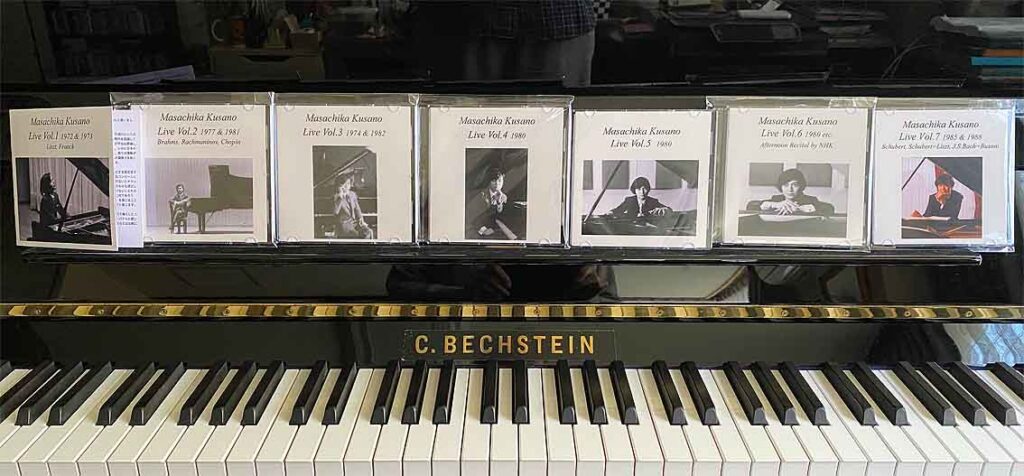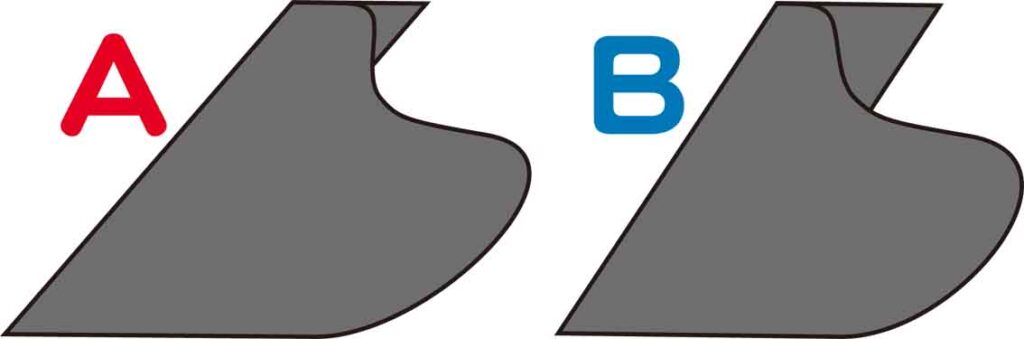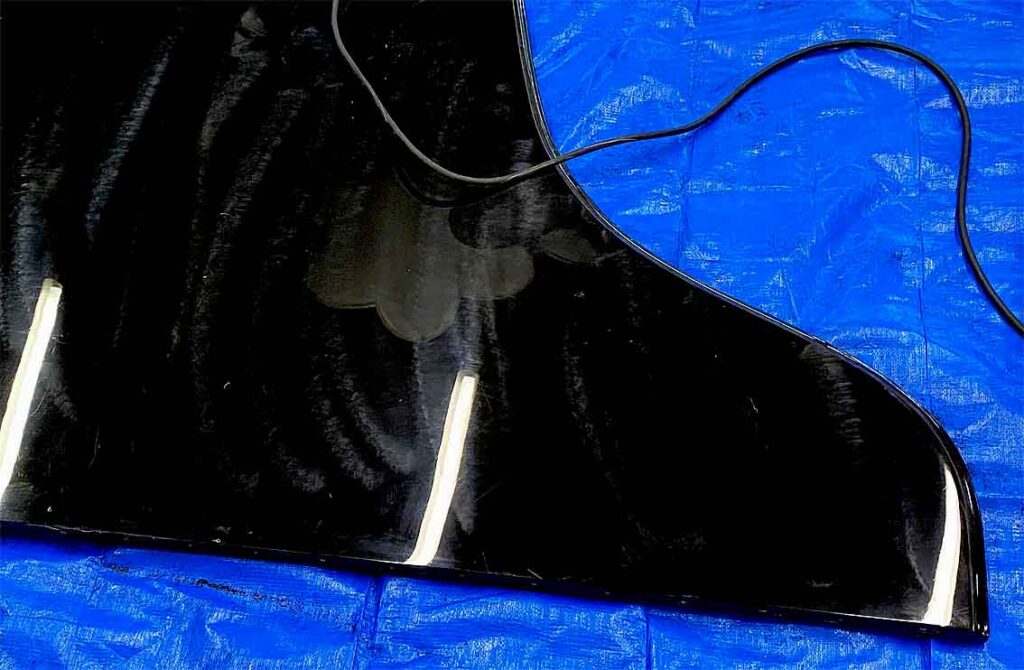BSクラシック倶楽部で、辻井伸行さんのサントリーホールでのコンサート(2022年)を視聴。
近年は(私だけの印象かもしれないけれど)ピアニストの世界もどこか芸能界のようで、あとからあとから優秀な人が新しい人が現れてくるから、よほどの人でもふっと忘れてしまうほど入れ替わりが激しい気がします。
辻井さんもそのひとりというつもりではないけれど、ずいぶん久しぶりに聴いた気がしたことは確かでした。
そこには、やはりこの人ならではの演奏があり、常に直球で、全身でぶつかってゆくところが爽快でもあり、これはこれだなあと思いました。
2025年のショパン年にも沿って再放送されたのか、舟歌とソナタ3番、そのあとにアンコールというものでした。
すでにピアニストとして相当のキャリアも積まれているあたり、聴こえてくるのはさすがというべきプロの磨かれた演奏であり、チケットを買って聴きに来た聴衆を満足させるだけの聴き応えを備えた人だということを感じます。
ただ上手いとか、弾けているというだけでなく、この「聴き手を満足させる」というところはとても大事なところ。
辻井さんの聴きどころは、終始潤いがあり、肉感があるところで、奏者の心情や感受性が明快な音に乗って、この人ならではの言葉になっている点などではないかと思います。
それがどうかすると作品と噛み合わない、もしくはもの足りないように感じるところもないではないけれど、厚みもあば逞しさもあり、なによりウソのない、偽らざるところから出てくる(ように聞こえる)演奏は、この人からしか聴けない特徴だろうと感じます。
また、必要以上に深いものを求めるがごとく内奥を追い回すこと、もしくはそういうことをやっていますよ、、というようなことはしないところが潔いし、だからこそ演奏には筋が通っているように感じます。
今どきは無個性でクセのない、偏差値の高い演奏が主流を成し、さらに日本人は専門家にも好評を得てかつ大衆にもウケること、、の両方を狙っているフシがあるから、その点でも辻井さんの演奏にはあざとさのない清潔さを感じます。
多くの若い優秀なピアニストが、本当の自己表現をするには至っていないのに、能力のジマンには余念がなく、要するに何が言いたいのかよくわからないままヘンな後味が残ることが多い中、辻井さんは自分がどういう演奏をしたいかが簡明で、こういうスタイルは一見すると普通なようですが、その普通であることは実際にはとても珍しいことであるし、それが個性のような気がします。
アンコールのひとつはエチュードop.25-12でしたが、op.25-11があまりに頻繁に弾かれるから、冒頭のミーミミミファミドミからしていささか食傷気味であるのに対して、この12番は劇的な波濤がこれでもかと打ちつけて、あらためていいなぁ!と思いました。
そして、聴く人に理屈抜きに「いいなぁ」というシンプルな印象を残すこと、これこそがいい演奏なのではないかと思います。